発達心理学者の間では、ピアジェはこどもたちの能力を過小評価しているとの共通認識は得られているが、どの理論も最もよくピアジェにとって代わるものかについては、いまだ意見の一致は得られていない。ある心理学者は情報処理アプローチの立場をとる。他方、知識獲得理論や社会文化的アプローチを支持する研究者もいる。
情報処理アプローチ
すでに述べたようにピアジェの考えに反論する実験の多くは、認知発達をいくつかの異なる情報処理技能(information-processing skills)、つまり環境から情報を集め分析する特定の技能の獲得としてみる研究者によってさかんに行われてきた。
さらに、標準的なピアジェ流の課題は、これらの技能とその課題が査定しようとする技能とを区分することに失敗していると彼らは考える。しかし、ピアジェ理論にどこまで異議をとなえられるかについては意見が一致しない。
たとえば、主要な問題である発達は一連の質的に区分された段階として理解されるものか、あるいは一続きの連続的な段階の過程として理解するほうがより適切なのかについて意見の一致は見られない。段階そのものの考えは破棄すべきだと主張する研究者さえもいる(Klahe,1982)。
彼らは質的に不連続な段階としてではなく、それぞれの技能はなめらかにかつ連続的に発達していくのだと考える。しかし、ほかの情報処理理論家たちは、情報処理技能そのものは漸進的(物事を徐々に進めていくさま)に進行していくが、それが実際は子供たちの思考において、不連続的な段階に似た変化を導くと考える(Case&Okamoto,1996)。
これらの立場をとる理論家はピアジェ学派と言われる。もう一つ別の新ピアジェ学派は、段階そのものはまさに存在しているが、それはより狭い知識領域においてのみ生じるのだと考える。たとえば、子どもの言語技能は、数学的理解、社会的推理などはすべて段階的に進むような発達過程を示すが、それぞれの領域はそれ自体の速度で進行し、相対的にほかの領域とは独立であるとされている(Mandler,1983)。
知識獲得アプローチ
発達心理学者の中には、幼児期以降、子どもと成人は本質的に同じ認知過程ならびに認知能力を持っているが、異なるのは主として成人の知識の土台が広範囲にわたるものである点だと主張する研究者がいる。
ここでいう知識(knowledge)とは、単に事実の集積ではなく、いかに事実が特定の領域において体制化されているかといった深い理解を意味する。知的獲得アプローチの例として、シーグラー(1996)の認知発達の重複波理論があげられ、この理論によると子どもは発達のいかなる時点においても問題解決のための複数の方法を持っているが、年齢や経験とともにある方略がより頻繁に選択され、別の方略はあまり選択されなくなるという。
この事実と事実の体制化との区分は、10歳のチェスの競技大会に出場した選手群とチェスについてはアマチュアの大学生群とを比較した研究において、明らかにされている。
無作為順序の数字の一覧表を記憶し、再生するように求めた場合は、大学生のほうが10歳の子供たちを大きく上回る成績であった。しかし、実際ゲームにおけるチェスの駒の配置を再生する能力を検査した場合は、10歳のチェスの熟達者のほうが18歳のチェスのアマチュアよりも良い成績を示した(Chi,1978)。
つまりこの二つの群を分ける決定的な違いは、認知発達の段階が異なるからではなく、領域固有的知識によるものだといえる。10歳のこどもはチェスの基本的な構造について深い理解を持っていたため、個々の駒の情報をより大きな意味のある単位に「チャンキング」し(たとえば、王様の横が攻撃を受けている)、意味のない駒の配置を排除し、その配置を体制化し再構築することができたのである。
認知発達における質的な移行というよりむしろ、子どもたちが年長になるに従いピアジェの保存課題を解けるようになることは、世界に関する知識が増えることによっても、説明できるかもしれない。
たとえば、量の数が、「多くの粘土」や「たくさんのおはじき」を意味づける決定的な特性であることがわからない子どもは、ただ視覚的に見かけの状態が変化しただけで、その数量が変化したと判断してしまう。年長の子どもは、「多くの」という本質的な定義特徴を学習したにすぎないのかもしれない。
この仮説が正しいとするなら、ある領域で保存を示すことに失敗した子どもでも、別の領域では保存を示すかもしれない。その領域に関する理解に依存するからである。このことは、幼稚園児を対象に、医者あるいは科学者が行った一連の「手術」の物語を聞かせる研究で検証された。
その物語に描かれた二つの手術のうち、一つは、ある動物をまったく異なった動物に見えるように変形するという手術であった。もう一つの物語は、ある動物を植物のように変形する手術をしたというものであった。

たとえば、子どもたちには以下のように教示された。
’’お医者さんが一頭のウマをを連れてきた(子供にウマの写真を見せる)。そして、黒と白の縞模様をその馬の体全体につける手術をし、尻尾を束ねる。そして馬のように鳴かないように訓練をし、またオート麦や干し草ではなく雑草を食べるように、牧場ではなくアフリカのサバンナで生きていけるように調教した。すべて終わるとこんな風な動物になった(シマウマの写真を見せる)。最終的には、この動物はウマだと思うか。それともシマウマになったと思うか。’’
ある動物を別の種類の動物に変える手術についてたずねると、就学前の子どもたちのほとんどが、保存に失敗した。およそ65%の子どもたちは、ウマが本当にシマウマに変わってしまったことに同意した。しかし、動物を植物に変形する場合、ハリネズミが本当にサボテンに変わったと判断したのはわずか約25%にとどまった(Keil,1989)。
これらの研究から、いくつかの領域においては、前操作期の子どもたちでも、視覚的な見かけ上の大きな変化を無視することが可能であることが明らかとなった。。それは、対象の持つ、眼には見えないけども本質的な特徴は依然として変わっていない、ということを学習していることを意味する。
社会文化的アプローチ(sociocultural approach)
ピアジェは、子どもとその子どもを取り巻く周りの環境との相互作用を強調したが、ピアジェの考える環境とは、直接的な物理的環境であった。子どもの社会的・文化的環境は、ピアジェ理論ではほとんど考慮されなかった。現実を理解するあり方はどんな子どもでも学ばなければならない。
すなわち人や男女はどんな役割を演じるように期待されているのか、子どもの文化においてどんな規則や基準が社会的関係を支配しているのか、などについて学ばなければならない。これらの領域にはすべてにおいて妥当な事実はなく、現実についての正しい見方も存在しない。
つまり、発達に対する社会文化的アプローチ(sociocultural approach)をとる学者は、子どもとは「真の」知識を探求する物理学者してではなく、ある文化に生まれ出た新参者として見るべき存在であると主張する。つまり子どもは、その文化の下に生まれた人になろうと、その文化の持つレンズを介して社会的現象をどう見るべきなのか、その見方を学ぼうとするのだと考える(Rogoff,2000)。
文化はさまざまな形で子どもの発達に影響を及ぼす。
1)特定の活動に対する機会を提供する
子どもたちは観察や経験をとおして、あるいは活動に関する情報を聴取することによって学習する。たとえば、水は砂漠地帯では乏しいために、カラハリ砂漠のクン族も子どもたちは、一つのコップから別のコップに水を注ぐ経験を通して保存の概念を獲得することは難しい。しかしシアトルやパリで育った子供たちは、砂漠で水脈を見つける方法を学習することはできないであろう。
2)特定の活動の頻度を決定づける
たとえば、伝統的な踊りはバリ島の文化にとって重要であるので、そこで育った子どもたちは踊りが上手になる。しかしノルウェーの子どもたちはスキーやスケートの熟練者になる。
3)さまざまな活動を関係づける
たとえば、陶器を作ることが重要である文化圏においては、子どもたちは粘土をこねて形づくる活動と両親との相互作用とを結びつける。おそらく作った壺を市場で売ることも関係づけるであろう。陶器を作ることが重要ではない文化圏においては、子どもたちは粘土をこねて形づくる活動は単に保育園での遊びとしか見ない。
4)活動における子どもの役割を制御する
多くの文化圏では、肉はスーパーマーケットで手に入れることができる。子どもたち(またその親たち)は罠をかけ、殺したり食用のための動物を飼育することはない。他方、ある文化圏では、子どもたちは幼いころから家族の食事を確保するため動物を捕まえたり、殺したり、あるいは食肉用の動物を飼育する方法を学ぶ。
このような認知発達についての考え方の起源は、ロシアの心理学者であるレフ・ヴィゴツキー(Lev Vygotsky,1934/1986)に見ることができる。ヴィゴツキーは、主としていわゆる従弟としての期間を通して、より熟達した人の指導を受けて、理解力を増し熟達していくのだと考えた。
熟達者は私たちの世界に関するより多くの知識を理解できるように、また新しい技能を獲得できるように援助する。彼はまた認知発達を二つの水準で区別した。
すなわち、一つは課題解決能力と言われる実際に顕在化される発達水準であり、もう一つは大人や、より知識の多い仲間の援助によって問題が解決される潜在的な水準である。
ヴィゴツキーによれば、もし特定の子どもの認知発達を十分に理解し、彼らに対して適切な指導を行うのであれば、その子どもたちの顕在化した水準と潜在的な水準の両方を知る必要があるとされる。
言語は社会的な意味のやりとりする主要な手段であるゆえに、ヴィゴツキーは言語発達を認知発達の中心課題と考えた。事実、彼は言語習得を子どもの発達の中で、最も重要な側面とみなした(Blanck,1990)。言語は新しい技能や知識を獲得する上で重要な役割を担う。
大人や仲間が新しい課題を解くのを援助していく中で、彼らとのコミュニケーションが子どもの思考の中に内在化する。そして、新しい技能を試みていく中で、子どもは自らの言語能力を使って自らの行動を導くようになる。すなわちピアジェが自己中心的な発話と呼んだ現象をヴィゴツキーは認知発達の中心的な役割を担うものと考えた。
つまり子どもは自分自身を相手に対話し、自分自身を導き方向づけているのである。この種の自己教示は、自己中心的言語と言われている。この過程、靴とはくという課題を子どもにやらせてみると、観察できる。子どもは以前に大人かから教わった靴のはき方を自分自身に対して教示していることが確認できるであろう(Berk,1997)。
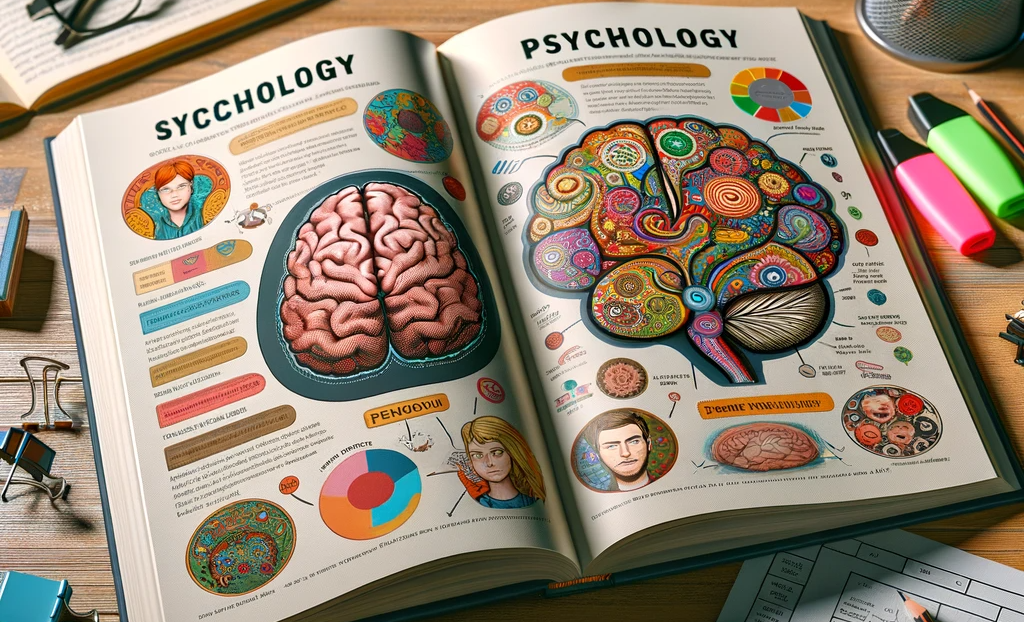

コメント