マイヤーとセリグマン(Maier&Seligman,1976)は、イヌを使って重要な実験を行った。彼らの基本的実験は二つの段階からなりる。
第一段階では、一方のイヌには行動次第(生体の行動によって制御される)で電撃が与えられるかどうかを学習させ、もう一方には電撃が制御できない事を学習させる。まず二匹のイヌを別々の箱に入れ、二匹同時に電気ショックを与える。そのとき片方のイヌAはそばにあるパネルを鼻で押すことによって、電撃を停止(制御)することが出来る。
もう一方のイヌBはくびき(自由を拘束するもの)に繋がれており、どんなことをしても電撃を止めることが出来ない(制御できない)。このとき制御条件のイヌが電撃を受けるときは、必ず繋がれているイヌも電撃を受けることになり、制御条件のイヌが電撃を停止するときは必ずつながれたイヌの電撃も解除される。
したがってA、B二頭のイヌは共に同じ回数、同じ時間だけの電撃を経験したことになる。第二段階でA、Bのイヌにそれぞれに電撃の回避条件づけの訓練が行われる。
両方のイヌをそれぞれ障壁によって二つの部屋に分けられた新しい装置の箱に入れられ、電撃の試行ごとに音が鳴らされる。電撃を避けるためにはその警告音が聞こえたらすぐに障壁を飛び越え、分けられたもう一方の部屋に移ることを学習する必要がある。
この結果、第一段階での制御条件のイヌAは、この回避反応を速やかに学習したが、繋がれていたイヌB(生体自身で制御できなかったイヌ)は、障壁を越えようとするそぶりさえ見せず試行が続くにつれなされるがままとなり、ついにはまったくの無力状態になってしまった。
マイヤーとセリグマンらは、これは第一段階でイヌBは「電撃が自らの制御を受けない(回避不能である)」ということを学習し、その制御不能さが第二段階での避けようとすれば避けられる場合でも電撃を避けることの学習、すなわち回避学習を妨げたと考え、また、このような現象を学習性無力感(learned helplessness)と呼んだ。
これらの実験例やその後の研究により、生体(人間)が抑うつ、無力感、無気力の状態に陥ってしまう理解には、その個人がそうした負の状況(経験)をどう認知し、予測するか、その原因を何に帰属させるか、などの点についての考慮が必要と強調されるようになった。
つまり、道具的条件づけにおいても「条件刺激の予報性(認知的要因)」での説明のように、認知的要因は重要で密接であると考えられる。
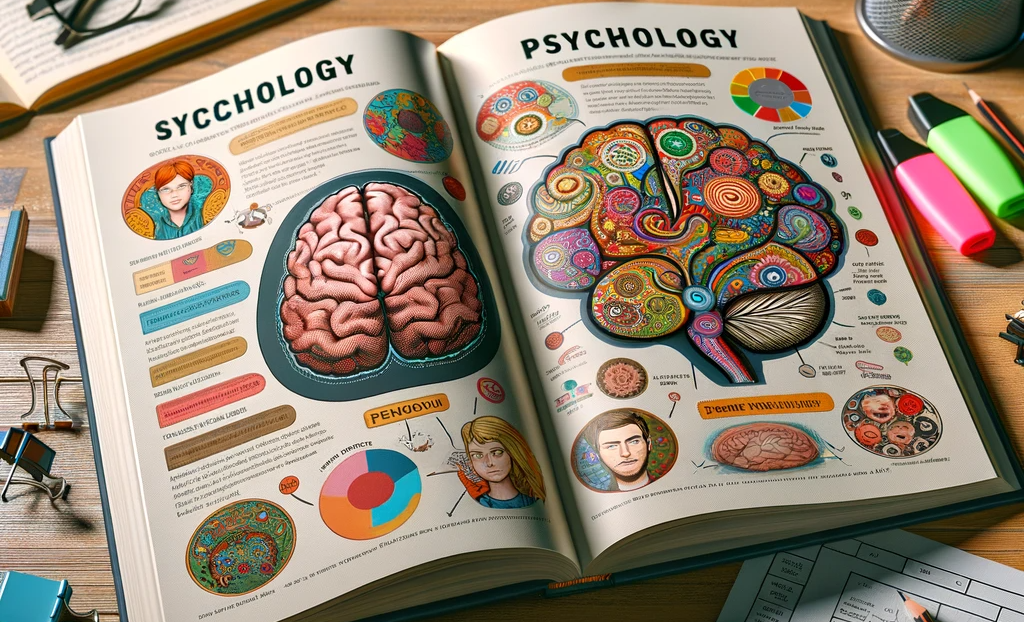
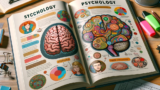
コメント