赤ちゃんに見られる愛着の違いを説明するために、研究者たちは、主たる養育者、すなわち母親のとる行動に多くの関心を集めている。その主なものとして、赤ちゃんの欲求に対する応答感受性(sensitive responsiveness)が安定した愛着を生み出しているのだとする知見がある。
安定した愛着を持つ母親は、普通赤ちゃんが泣くとすぐさま反応し、赤ちゃんを抱き上げ、そして愛情深く行動する。また自分たちの応答を赤ちゃんの欲求に密接の合わせようとする。(Clarke-Stewart,1973)。たとえば、乳児において、乳児が示す信号を見てとり、いつ授乳すればよいかを決め、また赤ちゃんの食べ物の好みに注意を払う。
対照的に、不安定愛着型:回避型(insecurely attached:avoidant)を示す赤ちゃんの母親は、赤ちゃんの信号に対して反応するというよりは、母親自身の思いや気分に基づいて反応する傾向が強い。赤ちゃんの泣き声に注意を払い反応するのは、母親が赤ちゃんを抱きたいと思う場合に限られており、それ以外では泣き声を無視してしまう(Stayton,1973)。
養育者の反応が乳児の愛着行動を規定する主要な要因とする考えに、すべての発達心理学者が賛同しているわけではない。赤ちゃんの持つ先天的な気質に注目する研究者もいる(Campos,Barret,Lamb,Goldsmith&Stenberg,1983;Kagan,1984)。
たとえば、「扱いやすい」気質を持つ赤ちゃんは、おそらく「気むずかしい」気質をもつ赤ちゃんよりもより安定した愛着を形成すると思われる。またすでに指摘したように、母の子どもに対する反応そのものは、しばしば子ども自身のとる行動の関数になる。
たとえば、気むずかしい赤ちゃんの母親は、赤ちゃんと遊ぶあまり多くない傾向がある(Green,Fox&Lewis,1983)。愛着様式は、赤ちゃんの気質と母親の応答との相互作用を反映していると考えられる。
反対に、愛着理論家たちは、養育者の「応答感受性」仮説を支持するデータを指摘する。たとえば、生後1年間における乳児の泣くことの変化は、泣くことに対する母親の応答の変化と比べて大きい。3カ月にわたる母親の応答は次の3カ月間における乳児のなく行動を予測し、乳児のなく行動が母親の応答を予測するよりもその効果は有意に大きい。
つまり、母親は乳児の泣くことに影響を及ぼしているのであり、しかもその程度は、乳児が母親の応答に及ぼす以上の大きな影響であると考えられる(Bell&Belsky,1972)。一般に、母親のとる行動は、安定的あるいは非安定的愛着を確立する上で最も重要な要因と言える(Isabella&Belsky,1991)。
また別の研究では、この論争に一つの答えを提供するかもしれない。愛着の型は、主として母親が退室したとき(愛着(attachment)-1)の赤ちゃんの苦痛の基づくのではなく、母親が戻ってきたときに赤ちゃんがどのように反応するかに基づいて分類されたことを思い出してもらいたい。
今日では、幼児の気質は前者を予想させるものであって、後者の反応を予測するものではないと考えられている。(Frodi&Thompson,1985;Vaughn,Lefever,Seifer&Barglow,1989)。
たとえば、「扱いやすい」気質の赤ちゃんは、母親が退室した際に明らかな苦痛を示すことはないが、母親が戻ってきたときに、喜んで母親を迎えるか(つまり安定愛着型を示す)、あるいは非安定愛着である回避様式を示すだろう。「気むずかしい」気質を持つ赤ちゃんは、母親が退室したときに明らかな苦痛を示すだろうが、母親が戻ってきたときには、求めて抱きつこうとするか(つまり安定愛着を示す)、あるいは非安定愛着の両価型を示すと考えられる(Belsky&Rovine,1987)。
すなわち、母親が出て行くことと戻ってくることに対する子どもの反応全体は、子どもに対する母親の応答と子どもの持つ気質との双方の関数であるといえる。
愛着形成後の発達
あかちゃんの示す愛着の分類は、その後、数年間にわたり再検査されたときでも、家族の生活環境における大きな変化がない限り、それはきわめて安定したものであることがわかっている(Main&Cassidy,1988;Thompson,Lamb,Estes,1982)。ストレスの多い生活上の変化は、赤ちゃんに対する親の応答に影響を及ぼす可能性があり、またその赤ちゃんの安定愛着感にも影響を及ぼす。
初期の愛着の様式は、子どもたちがその後の新しい経験をどのように処理するかにも関係があるように思われる。たとえば、2歳児を対象に、道具の使用を要求する一連の課題を与えた研究がある。
課題はその子どもの能力で解けるものと、まったく困難なものがあった。生後12カ月時に安定した愛着と評価された子供たちは、課題に熱心にまた根気よく取り組んだ。困難な課題においても、めったに泣いたり、怒ったりすることはなく、むしろその場にいる大人に助けを求めた。
しかし、同時期に不安定な愛着と評価された子供たちは、まったく異なった行動を示した。容易に欲求不満や怒りを示し、めったに助けを求めることはなかった。大人からの指示を無視したり拒絶する傾向があり、またすぐに課題を解くことをあきらめてしまう傾向が見られた(Matas,Arend,&Sroufe,1978)。
これらの研究は、生後2歳までに安定愛着を示した子どもたちは、新しい経験に十分に対処できる準備ができていることを示している。しかしながら、子どもたちの示す初期の愛着の質が、直接的にその後の問題解決能力を左右するものかどうかについては、はっきりとした確証が得られているわけではない。
幼児期に子どもたちの欲求に応ずる両親は、おそらく、その後の児童期早期においても効果的な育児を行い続けるはずである。つまり、自律性や新しい経験に取り組む努力を促し、また必要な場合は援助しようとする。つまり、子どもが有する能力は、初期の2歳児に見られた関係というよりむしろ、現在の親子関係の状態を反映しているのかもしれないのである。
さらに、子どもたちの持つ気質は、すでに見てきたように、ストレンジ・シチュエーション法(愛着(attachment)-1)の下での行動に影響を及ぼし、さらにはまた就学前における能力にも影響を与えていると考えられる。
愛着類型の文化差
エインズワースはウガンダにおいても調査を行ったが、大部分の研究はアメリカの中流階級を対象にしたものだった。その後研究で、ストレンジ・シチュエーション法に基づいて分類された子供の愛着類型の割合には、大きなばらつきがあることが示唆された。
| 回避 | 安定 | 不安 | |
|---|---|---|---|
| スウェーデン | 21.57% | 74.51% | 3.92% |
| イスラエル | 8.43% | 56.63% | 33.73% |
| イギリス | 22.22% | 75.00% | 2.78% |
| 日本 | 0.00% | 68.33% | 31.67% |
| ドイツ | 48.9% | 32.65% | 12.24% |
| オランダ | 34.15% | 5.85% | 0.00% |
| アメリカ | 21.70% | 66.04% | 12.26% |
【*ストレンジ・シチュエーション法で測定した愛着の割合は、それぞれの文化で劇的に異なる。数名の乳児や無秩序型に分類された乳児については信頼できる判定ができないため、割合を合計しても100にはならない】
これらの文化差は、ストレンジ・シチュエーション法が多くの文化における母子関係の質を測定するのに不適当であることに起因するかもしれない。たとえば、日本の乳児は想起には基本的に母親から分離されない。そのため、ストレンジ・シチュエーション法でなされる強制的な分離は、乳児を脅えさせ、結果として「不安定:不安」の類型に入れられやすくなる可能性がある。
一方、ドイツの子どもには早期から母親から独立するよう促されるものもいる。ストレンジ・シチュエーション法における彼らの反応は、実際には一人でいることに慣れていることを示しているに過ぎないにもかかわらず、「不安定:回避型」を示唆する可能性がある。
これは、文化によって親子関係の様式に違いはないと主張しているわけではない。むしろ、ストレンジ・シチュエーション法の結果は子どもの文化環境内で理解されるべきであり、ある文化が別の文化よりも安定した子供を育てるという誤った解釈はしてはならない。
日本と欧米の愛着研究
これらの愛着理論を整理し、愛着概念の文化的な差異あるいは共通点に注目することで、より普遍的な枠組みが提出されている(Rothbaum et al..2000)。安定した愛着の先行要因、発達過程、およびその特性についてのこれまでの考え方を、3つの仮説により整理できる。
①感受性仮説
安定した愛着が生まれるかどうかについて大きな要因として、親が子どもの出すサイン(信号)に対して敏感に反応するかどうかが挙げられる。たとえば、乳児が危険を察知し、助けのための信号を出す。親は正確に知覚し、適切に子どもからの助けの求めにタイミングよく応答するかどうか。欧米の研究でこの仮説は幅広く実証されている。
②有能性仮説
安定した愛着の中にいる子供はそうでない子どもと比べて、社会的、情緒的に有能になっていく。
③安全基地仮説
子どもは、親により守られ慰められると感じると、周りを探索していくことができる。
これらの仮説を日本に当てはめる際には、この各々の仮説が、日本での研究をもとに修正されなければならない。
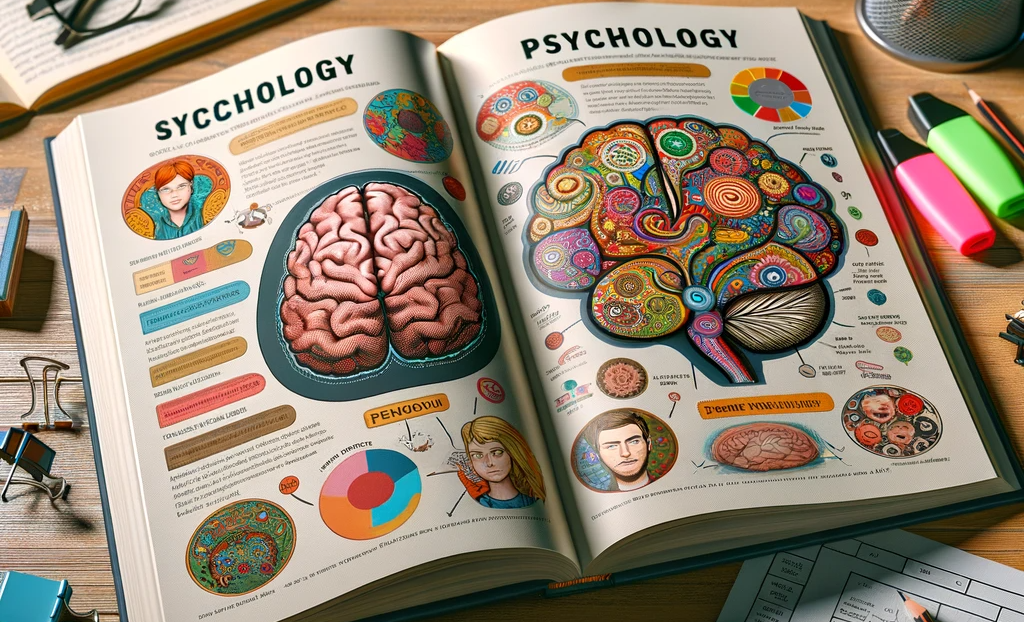

コメント